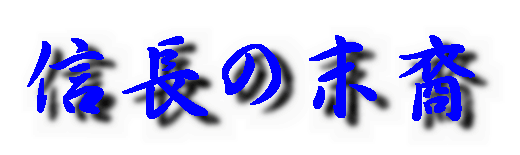
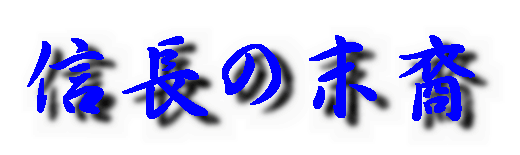
| ひでこ |
| 生没年 | ?〜1632 | 信長の三女? |
| 幼名・別名・官職 | 冬姫 | 生母 | 不明 |
| 筒井定次に嫁ぐ。 生年、生母などは一切伝わらず。 三女であろうと思われるが、確定されているわけではない。 筒井定次は大和一円支配を信長より任された筒井順慶の養嗣子である。 入嫁は天正六年(1578)といわれている。 『多聞院日記』には天正三年(1575)二月に 「信長ヨリ筒井順慶へ祝言在之、塙九郎左衛門尉送テ来」 と書かれた箇所がある。 この「祝言」順慶に対し子の定次と秀子の婚姻の件を指すと考え、もう少し早かったのではないか と、考える向きもある。 これに対し、「祝言」は順慶自身と信長の身内の女性との婚姻を指しているという説もある。 しかし、順慶へ嫁いだとする女性はどの系図系譜にも見あたらない。 とにかく、婚姻を天正六年として考えてみる。 信長の娘の婚姻年齢を見てみよう。 長女五徳=9歳、次女冬姫=9or12歳、四女永=8歳、五女=7歳・・・・ ならば秀子も、この時7〜12歳というところか。 8〜9歳あたりと考えたほうが自然だろうと思われる。 逆算すれば秀子の生年は元亀元〜二年(1570〜1)だろうと推測される。 (あくまでも推測である。) 本能寺の変後、明智方、秀吉方どちらともつかぬ態度を見せた順慶は、「日和見順慶」などと 後世でも陰口をたたかれる。 それでも順慶は秀吉政権のもとでも大和の支配を安堵されていた。 その陰には二度も養嗣子定次を秀吉へ人質として差し出していたこともあるのであろう。 秀子も他の兄弟姉妹と同様、本能寺の変より一転して 「元は家臣であった秀吉へ差し出された人質の妻」となってしまったのである。 天正十二年(1584)、順慶の死により定次は家督を嗣いだ。 定次は秀吉のもと小牧長久手の戦いや四国征伐などで功績をあげ羽柴姓までも賜るのだが、 大和一国支配という権力は剥奪されてしまうのである。 かわりに伊賀へ転封、20万石であるから秀吉から得られる待遇としては冷めたものもあろうかと思う。 関ヶ原の戦いでは東軍に加わり所領は安堵されたが、慶長十三年(1608)家中騒動により改易される。 大坂冬の陣に際して大坂方に内通していたとして自刃を命ぜられた。 だが、秀子の動向は伝わっていない。 |
| 末裔 |
|